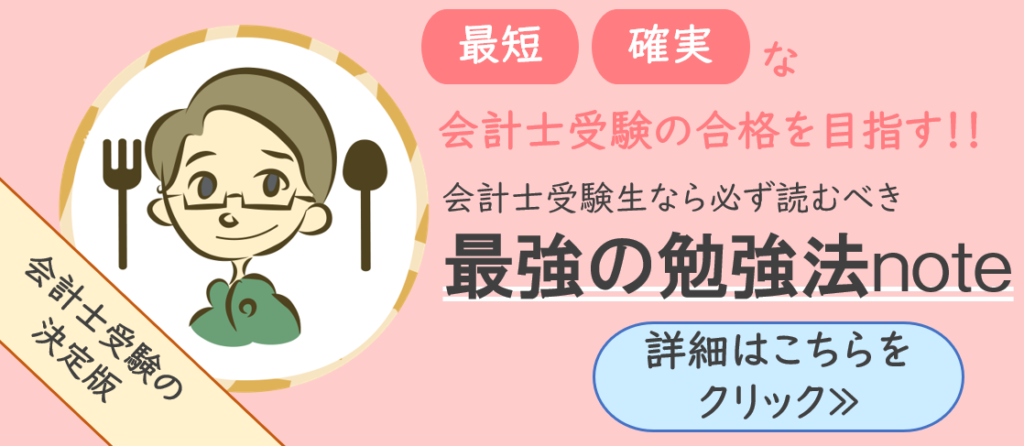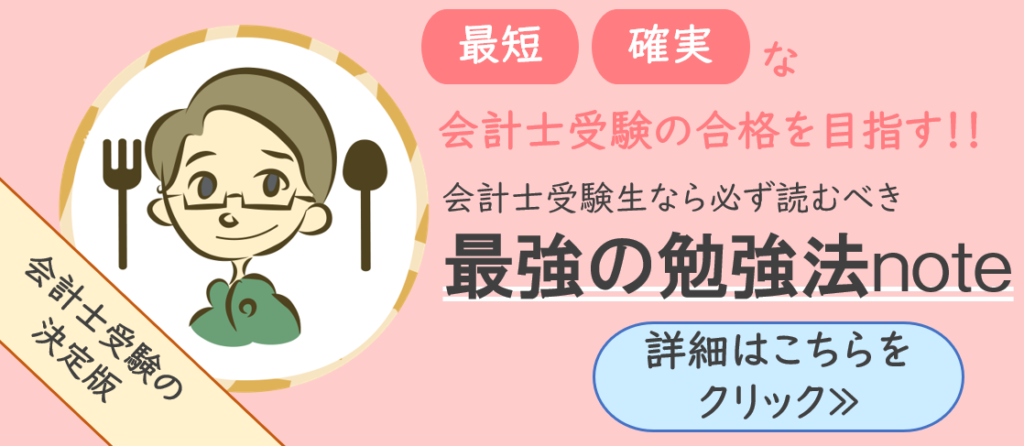「会計士 勉強法」で検索しても、公認会計士受験生が求めているような勉強法に特化した記事が見つからなかったため、自身の経験を生かして体系化してみた。
ちなみに想定読者はこんな方に設定して書いていきます。

効率的な会計士試験の勉強法がわからない
短答は合格できたけど論文の対策を全然していない
科目別に論文用の勉強法を知りたい
僕は大手の監査法人で次世代の監査の研究をしている現役の公認会計士です。
僕自身は2年半の学習で論文まで合格できました。でも、一緒に勉強していた友人は1年で合格しました。
実は、この方法のアイデアはその友人に教えてもらった方法です。短答にも受かっていなかった僕も実践したら、ホントに1年半で合格できたので、効果は保証します。
→追記:職場に2014年の論文1位合格者がいたので話を聞くと、だいたい同じような勉強をしていたようなので、信頼性はかなり高そうです。
受験全般を通して守るべきルールなど、受験全般の基本的な考え方は、公認会計士になるための具体的な勉強法:短答編を参考にしてほしい。受験全体の一覧は「【会計士受験の勉強法】短期合格のための総まとめ」に集めています。
公認会計士試験に合格するための具体的な勉強法~論文編~

全般(思い出し作業を覚えよう)
論文試験は、とにかく覚えることの多い科目試験だ。覚えることを避けている人は、なかなか超えるのが難しい壁だろう。逆に、効果的な方法を身に付けて、それに従って勉強していると、思ったより簡単に合格できる試験と感じるだろう。
さて、論文の勉強をする上で、是非身に付けて頂きたい方法が2つあるので、ここで紹介したい。
- 復習を高速回転させる教材作り
- 思い出し作業
僕のブログではさんざん紹介しているため、詳しい説明は省略します。初めて来た方は下記の関連記事をご参照ください。
関連記事:「会計士受験 ~必ず読むべき最短合格のロードマップ~」
思い出し作業は受験全体で使う最強のメソッド
科目別の学習も基本的にすべてこの「思い出し作業」で行う。
あえてネーミングを”作業”としているには理由があり、論文の学習を勉強と考えずに、”作業”をこなすことととらえて淡々と実力をつけることが短期合格に必要だと考えているからだ。
そもそも私がこの記事を書こうと思ったもの、この方法をみなさんに知ってもらいたいからで、それだけ得るものが大きい方法だということだ。ぜひ、バカになったようにそのままの方法で実行し、その効果を実感してほしい。
【会計士受験】科目別の具体的な勉強法~論文編~
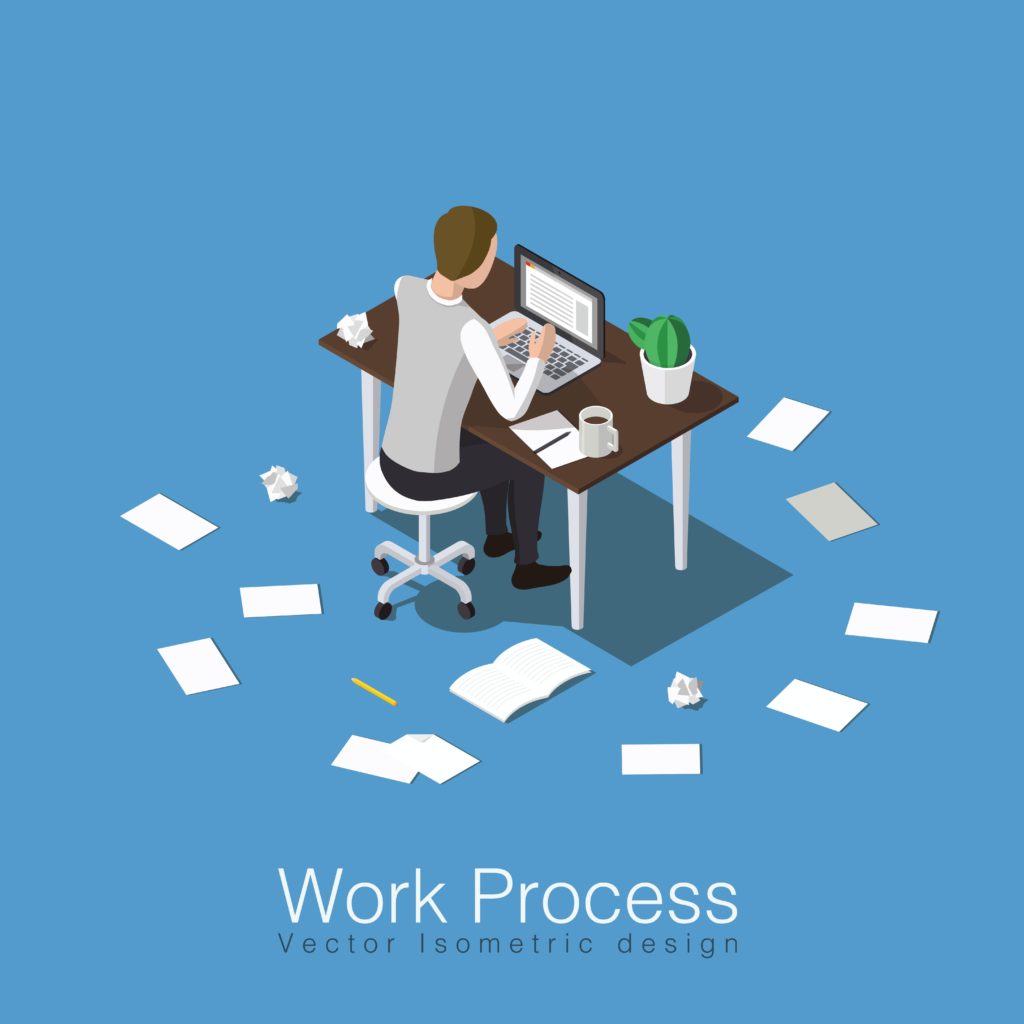
基本方針:各基準の基本的な理論(結論の背景)を思い出し作業で覚える。(大原の場合、ポケットコンパス+αでいい )
答練については、普段の学習では書くことを一切しない(してはいけない)ため、実際に書く練習として、必ず受けるようにしよう。
POINT 基本的な部分を抑えれば十分で、試験中も取るべきところを
と見直して、確実に点を積み重ねることが大切だ。
少し補足すると、仮に計算問題で苦手分野(例えば、連結CFなど)があるならそれをなくす努力はすべきだと思う。
基本方針:テキストの文章が答えになる問題を作り、それに頭の中で答える思い出し作業を繰り返す。適宜、答練問題も取り入れ、監査の中心的理解を目指す。 私が自作した問題も載せておくのでぜひ参考にしてほしい。
答練については、会計学同様、普段の学習では書くことを一切しない(してはいけない)ため、実際に書く練習として、必ず受けるようにしよう。
POINT ポイントは、思い出し作業を続けていると、自分の弱い分野や論点がわかってくる。そこを一つ一つつぶしていこう。あまり範囲が広くないことを実感するはずだ。
ちなみに私は、上の自作問題の思い出し作業のみで、ほとんど時間を割かずに、1番点数が安定した得意科目になった。
基本方針:理論を重点的に行う。できればLECの池邉先生の論文用のテキストを入手し、思い出し作業をしよう。
答練については、短答と同じで試験対策が重要=取捨選択がカギとなるため、一回一回の答練を大切にしよう。なお、復習は理論だけでOKだ。
POINT 論文対策として計算はほとんどないと言っていい。試験本番を考えた場合、当たるかどうかわからない計算問題にかけるより、基本的な理論で点を積み重ねる努力の方が、対策としては効果的だ。もちろん、計算を完全に疎かにしていると、痛い目にあう。
基本方針:論文用の問題集(論証例)をひたすら思い出し作業で覚える。
答練については、毎年、TACか大原どちらの専門学校の予想問題が的中する傾向にある。
前日にやった答練がそのまま出るようなことも珍しくない。ヤフオクなどで答練を手に入れ、一つ一つ思い出し作業でインプットしよう。
POINT そうは言っても、すべての論証例を暗記するのは難しい。その年の予想や、傾向に合わせて取捨選択することもいい。それと、答練の成績を気にしない方がいい。私も答練では偏差値45を超えたことのない苦手科目だったが、本試験では偏差値65を出し、まったく心配は不要だった。
基本方針:問題集を3~4回繰り返し解くこと。細かい論点を忘れやすいため、1時間くらいですべての項目の復習ができるように情報を集約することを意識して学習を開始することが大切(大原の場合は、ポケットコンパス)。
答練については、あまり難しすぎる問題は、やらなくていいと思う。基本的な問題+近年の頻出論点(最近だと組織再編税制など)を中心に復習すれば十分だ。
POINT 基本的に、各専門学校の問題集を完璧にしていれば、特段気にする必要はない。強いてポイントをあげると、時間がかかるため短答に合格していなくとも、学習を開始することが大切だと思う。
基本方針:計算ができることは前提。残りの時間でテキストを理解したら、基本用語とその意義を覚えることに費やそう。
答練については、練習する問題の数が限られている科目のため、普通の問題集感覚で解き、復習するだけで十分だ。
POINT 意外に思われるかもしれないが、経営学は暗記科目だ。通常の計算ができることは絶対条件だが、あとは基本的な用語の意義を思い出し作業で覚えると、それ以降は特段対策が不要になる科目といえます。
なお、各科目より詳細は勉強法を別記事にしているため、物足りない方はぜひこちらもご覧ください。
選択科目は、僕自身が経験した経営学しか実体験を書けないのでご了承ください。論文科目です。
まとめ:公認会計士の論文式勉強法

陳腐な言葉だが、明けない夜はないのだ。最も大切な姿勢は「絶対に、絶対に諦めないこと」。
たとえ、暗闇の中で一筋も、、、ほんの少しの光さえ見えなくても、少しでも前に進むことです。
ただ、会計士試験の場合は、「毎日1歩でもいいから」進めばいいといえるほど甘くないのも事実。「10歩進むと決めたら必ず10歩進み、頑張ってあと1歩進む努力」をする。合格できる受験生はみんなそういう努力をしていますよ。
僕はこのブログで会計士になるための勉強法をかなり詳しく解説しています。紹介している方法をちゃんと実践できれば、必ず合格できると思います(^^)
 【公認会計士受験】勉強法まとめ・最短合格のロードマップ
【公認会計士受験】勉強法まとめ・最短合格のロードマップ
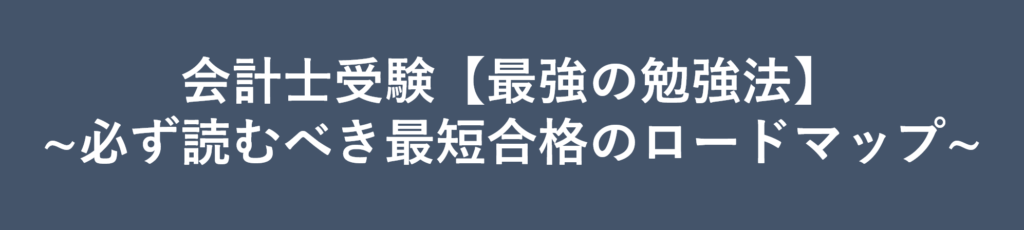
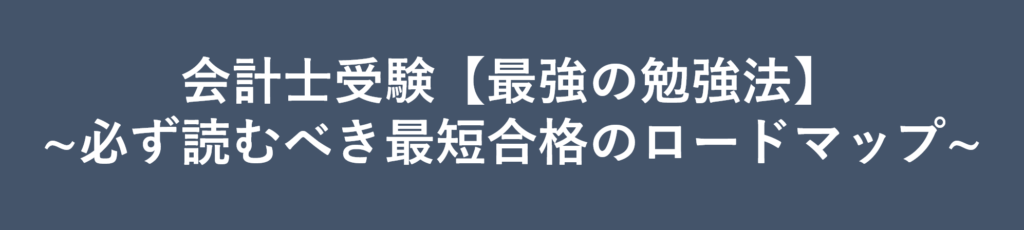
公認会計士の受験勉強をはじめると高確率で挫折します。
では、いつ挫折するか。それは、ちゃんと講師の言う通り、真面目に勉強しても、答練の点数が伸びない、本試験に合格できなかった時です。
そして、多くの受験生が自分の勉強法が正しいのか分からない状態で、未知の領域に向かって、やみくもな努力をしています。
公認会計士の受験生向けの勉強法まとめ「短期合格へのロードマップ」では、全コンテンツが実践的かつ具体的で、日々の学習に実際に落とし込めるツールになっているため、モチベーションを高めながら着実な成長が可能です。
さらに、質問サポート、”合格時”と”断念時”の両方のキャリア相談まで付いていて、まさに会計士受験における完全版といえる設計です。
会計士受験で人生変えたいなら、その入り口は「短期合格へのロードマップ」で。
正直な話、全ての受験生が必読の内容です(無料なのでサクッと読んじゃってください♪)。
■詳細はこちらから↓