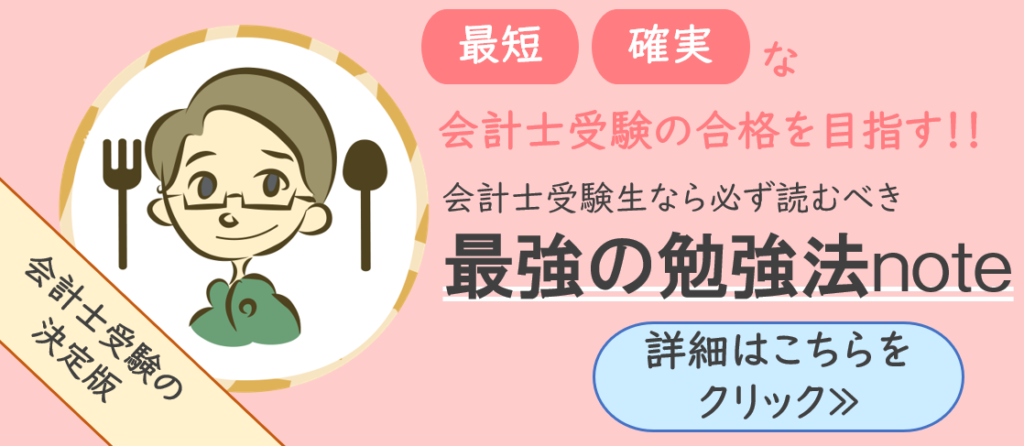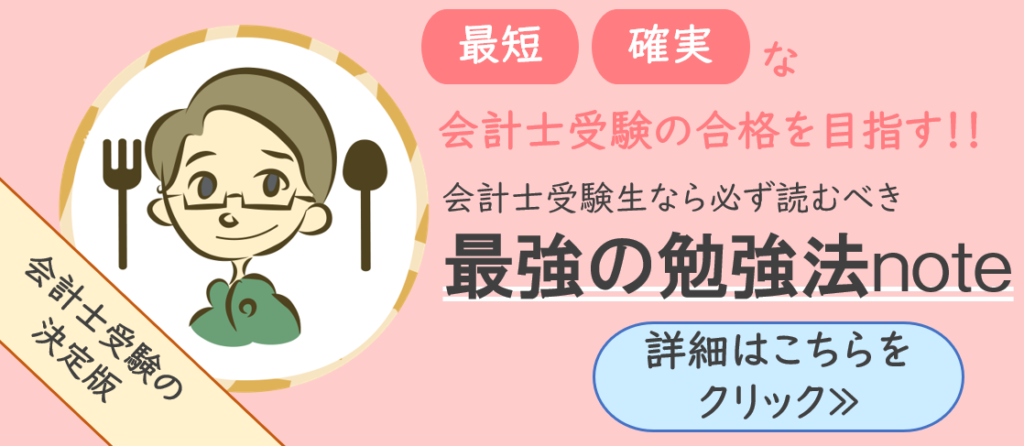「会計士 勉強法」で検索しても、公認会計士受験生が求めているであろう勉強法に特化した記事が見つからなかったため、自身の経験を生かして体系化してみた。
想定読者はこんな方に設定して書いていきます。

効率的な会計士試験の勉強法がわからない
特に短答に向けてのテクニックを教えて
科目別に具体的な勉強法も知りたい
ぼくの経緯~記事の信頼性~
僕は大手の監査法人で次世代の監査の研究をしている公認会計士です。
受験期間は、2年半で平均的が受験生ですが、勉強法の勉強はかなりしてきた方だと思うので、今回はその経験を紹介します。
なお、私の場合、仕事は完全にやめ、試験勉強に専念することにした。 社会人が仕事と両立して合格する方法は、実体験がないため、無責任なことは言えませんが、学習する上での基本的な方針は変わらないと思う。
公認会計士受験に合格するための具体的な勉強法~短答編~
大きく分けて、2つのテーマで解説していきます。
- 受験全般を通して守るべきルール【メンタル面】
- 具体的な科目別の勉強方針【テクニック面】
【会計士受験】受験全般を通して守るべきルール~メンタル面~
受験全体を通して重要なことが何点かある。
- 絶対に合格すると決意すること
- 期限を決めること
- 専門学校の教材を使うこと
- 忘却曲線を強く意識すること
- 日常生活全体として合理的な選択をし続けること
詳しくに見ていこう。
最も大切で、これさえあれば絶対に合格できるという唯一の条件は、「絶対に合格すると決意すること」だ。
ぼく自身、会計士試験に合格してからは、決意すれば、人生でやりたいことは何でもできると思っている。必要な犠牲を払う覚悟と決意さえあれば。
なんでもそうだが、何かを得るためには何かを犠牲にしなければならない。その覚悟ができて、必要は努力をすれば、どんな試験でも必ず合格できる!!
2番目に大切なのは、「期限を定める」ことだと思う。
1年間で必ず合格すると自分自身に誓い、周囲にもそれを公言しよう。
仮に当初設定した期限内に合格できなかった場合、大いに悔もう。そうした気持ちのセッティングが長い受験生活を支えるための、基本的な内的モチベーションとなる。
大原にしろ、TACにしろ、長年の実績がある学校の教材は、あらゆる人にとって合格するための最も効果的かつ効率的なツールとなる。
自分は想像もしなかったが、受験生の中には独学で勉強されている方が一定数いるようだ。独学での合格を目指す場合でも、市販の本を集めて勉強することは絶対に避けよう。
なお、どの学校を選ぶかは、好みによると思う。ただ、どの学校を選んだとしても、会計士試験が相対試験であることから、最終的に合格者の9割以上を輩出する大原・TACの教材を使うことになるのは間違いない。
相対試験とは、問題が100点満点の試験で問題が10問あったとして、一人も解けない問題が存在した場合にその問題には点数が配点されない。つまり、みんなが解ける問題を解ければ、問題なく合格できる試験だということだ。
技術的な話になるが、「忘却曲線を強く意識する」ことは、未知の分野を学習する上でとても大切な方法だ。
忘却曲線については、非常に大切で受験生にとっては必須の理論なので、関連記事「受験に必ず合格するための基本的な戦略【受験には戦略が必要】」は是非読んでください。
要は、人の記憶は1日たてばほとんど忘れてしまうが、忘れる前に復習すれば、記憶の大部分を定着させることができるということ。
1日もしくは数時間の間に、同じ問題を解く癖をつけると勉強がだいぶ楽になる。そして、勉強するのが楽しくなる。
忘却曲線や記憶のメカニズムについては、茂木健一郎著の「脳を活かす勉強法 奇跡の「強化学習」![]() 」が読みやすく、勉強する上で記憶を構築する方法を効果的に身につけることができるため、勉強に疲れた時などに気分転換に読んでみることをお勧めします。
」が読みやすく、勉強する上で記憶を構築する方法を効果的に身につけることができるため、勉強に疲れた時などに気分転換に読んでみることをお勧めします。
最後に、少しシビアな話をしたい。
いつまでも合格できない受験生の傾向として、”学校に来ても友達と受験に関するおしゃべりばかりしている”というものがある。付き合う友人は、慎重に選ぶべきだ。
どこの専門学校に通っても、自習室を利用しても、学校の中で公認会計士講座は最も難関のコースだ。
受験生の多くは、その難関試験を目指す自分を特別な存在と考えるようになる。そして、他のより難度の低い資格試験を見下し、学校の中で大声でおしゃべりをしている。絶対にそうなってはいけない。
話がそれたが、「日常生活全体として合理的な選択をし続けること 」は、勉強の習慣をつけ、生活全体を受験モードにする。
短期合格には欠かすことのできない態度であることは、いつも念頭に置いてほしい。
具体的な科目別の勉強方法は、それぞれの学習進度や短答・論文で異なるため、一つ一つ分類して後述していこうと思う。
【短答受験用】具体的な科目別の勉強方針~テクニック面~

短答式受験向けの全般的な勉強方針
最終目標は論文に合格することなので、そこを見据えて勉強することが大切だ。
具体的には、新しい知識を科目ごとに一つ教材に集約しよう。
集約する教材は、専門学校のテキストが一番いい。この試験は、カバーしなければならない範囲が膨大であるため、覚えた知識を忘れる前に復習できる環境作りがとても重要になる。
このあたりの話は、僕がおススメする「思い出し作業」という勉強法があるため、こちらの関連記事をご参照ください。
関連記事:「会計士受験 ~必ず読むべき最短合格のロードマップ~」
また、正確な知識を身につけることも大切だ。
当たり前のように聞こえるが、私たちの普段の会話の中では、日本語を曖昧なまま使っていることが非常に多い。
実際に、過去門を解くとわかるが、正確な日本語を意識し、正確な知識を身につけていなければ、ちょっとした日本語の問題でミスを連発してしまう。
そして、繰り返しになるが、絶対にあきらめないことだ。近年、短答式試験の難化が激しい。
裏返せば、短答をクリアすると、論文は思った以上に点が取りやすい試験であると気づく。短答を合格すれば、会計士試験の合格は近いと思っていいだろう。
【会計士受験短答式】科目別の勉強方針

基本方針:テキストの例題と問題集が基本。各基準ごとに理論を合わせて学習することが近道だ。
計算を身につける際のポイントは、各基準・各トピック(ストック・オプションなら、ストック・オプション)のすべてのパターンの問題を短時間でまとめて解こう。
よく簿記は、反復トレーニングが大切といわれるが、この意味は、”下書きパターン”を体に浸み込ませるということだ。
合格できる人たちは、問題を見た瞬間から、それを解くための下書きを反射的に書き始め、まるで手や下書きが勝手に解答を導いていく感覚を持っている。逆に、その感覚を早く身につけることが必要だ.
POINT そのためには同じ項目の問題を、「まず普通に解き→すぐ解答を見て→また、同じ問題を解く」という一連のトレーニングを一気に行うことが最も効果的だ。
各科目、より詳細な勉強法を解説しているので、関連記事を貼っておきます。
関連記事:「【会計士受験の勉強法】財務会計論で合格レベルになる方法」
基本方針:財務会計論と同じだが、テキストの例題と問題集が基本。各単元ごとに理論を合わせて学習することが近道だ。
答練について、スピード勝負の科目で、平均点も低い傾向にある。80点満点の試験と思い、70点を目指す意識で、捨てる問題をはっきりさせよう。
POINT 計算も理論も、基礎を抑えた後は、答練対策に時間を当てよう。具体的には、”問題の取捨選択能力を鍛える”ということだ。できる問題から解いていき、出来そうにない問題をきっぱりと捨てる意識が非常に重要だ。
その意味でも、一回一回の答練にキチンと向き合う必要性が一番高い科目といえる。また、この科目はコスパが悪いので、そもそもあまり多くの時間を割かないことも大切だ。
関連記事:「会計士勉強法】管理会計論で合格レベルになる方法」
基本方針:①まずテキストを理解し、②肢別(○×)問題集で細かい知識を覚える。③その後、監査基準で監査の中心的理解をする。コツでもなんでもないが、逆にこれしかない。
答練については、細かい知識に頼りすぎずに、中心的理解で解くことを心がけよう。
監査論は、短答でも論文でも、監査という仕事に対する中心的理解が非常に大切だ。
POINT 中心的理解とは、実際の実務の現場をイメージし、「理論的にはこうするべきだけど、コスパ悪いからこのぐらいがいいよね~。」みたいな感覚だ。現場を知らない受験生は、監査基準に照らして、考えるとよい。
私の場合、当初は重箱の隅をつつくような細かい知識を覚えることを目指していたが、結果点数は伸びなかった。
論文の勉強を始め、中心的理論の暗記を始めたところ、短答の点数が飛躍的に伸びた.
試験を受けている最中の感覚も、知識を引き出す感覚から、”監査ってこういうものだから、この場合はこれでいいんじゃないかなあ”という感覚的な判断をしている感覚に変わった。
その意味でも、監査基準を原文で3~4回読むと良い。どの科目もそうだが、基準の原文というものは、その道のプロフェッショナル達が非常に高度な議論の上で作られたものだ。
一つ一つの言葉の使い方がどれも本質的で、意味の深い文章になっている。数回通して読むだけで、監査論に対する理解がかなり進んでいることを実感できるはずだ。
具体的な論文の勉強法は、論文編を参照してほしい。ただし、まず細かい知識をある程度インプットをおろそかにするとやはり点数は伸びないことを付け加えておく。
関連記事:「公認会計士試験に合格するための具体的な勉強法~論文編~」
関連記事:「【会計士受験の勉強法】監査論で合格レベルになる方法」
基本方針:監査論と同じで恐縮だが、テキストと肢別(○×)問題集を丁寧にやることだ。
暗記科目と思われがちで、暗記だけである程度点が取れるのであまり悩むひとは少ないかもしれない。
一つポイントを言うと、企業法は、短答でも論文でも”理解”を求められる科目ではない。そのため、短答の際は、より多くの問題を解いた方が勝つと言える。市販の問題集なども購入し、より多くの問題に触れよう。
暗記が苦手という方は、たんに問題集の回転数が足りないだけなので、ただの努力不足であることを認識してほしい。
関連記事:「【会計士受験の勉強法】企業法で合格レベルになる方法」
さいごに

最後に注意したいのは、受験生活が長引く人は、この短答式試験で行きづまっていることが圧倒的に多いということ。
ベテラン受験性(=試験範囲の勉強は一通り終えたが、合格できずにいる人)となった方にとって重要なことは、合否の如何にかかわらず、論文式試験の勉強に必ず移行する方が良いでしょう。
特に会計学、監査論においては、論文の暗記型の学習が、短答式の問題に非常に有効であることを知っていてほしい。
僕はこのブログで会計士になるための勉強法をかなり詳しく解説しています。紹介している方法をちゃんと実践できれば、必ず合格できると思います(^^)
 【公認会計士受験】勉強法まとめ・最短合格のロードマップ
【公認会計士受験】勉強法まとめ・最短合格のロードマップ
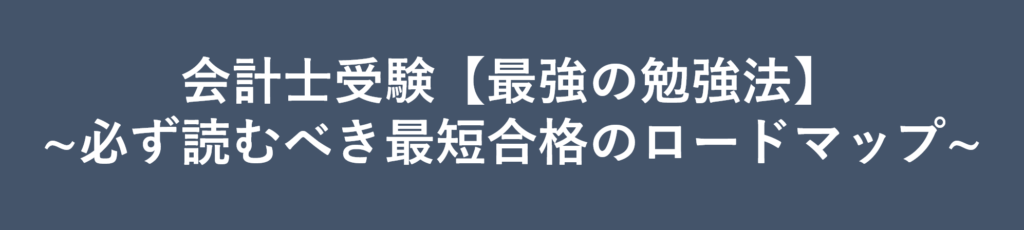
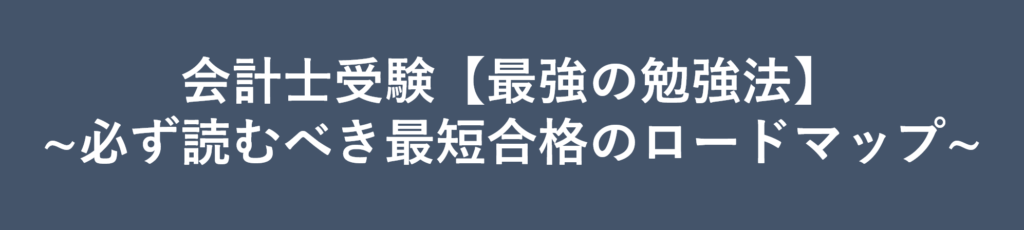
公認会計士の受験勉強をはじめると高確率で挫折します。
では、いつ挫折するか。それは、ちゃんと講師の言う通り、真面目に勉強しても、答練の点数が伸びない、本試験に合格できなかった時です。
そして、多くの受験生が自分の勉強法が正しいのか分からない状態で、未知の領域に向かって、やみくもな努力をしています。
公認会計士の受験生向けの勉強法まとめ「短期合格へのロードマップ」では、全コンテンツが実践的かつ具体的で、日々の学習に実際に落とし込めるツールになっているため、モチベーションを高めながら着実な成長が可能です。
さらに、質問サポート、”合格時”と”断念時”の両方のキャリア相談まで付いていて、まさに会計士受験における完全版といえる設計です。
会計士受験で人生変えたいなら、その入り口は「短期合格へのロードマップ」で。
正直な話、全ての受験生が必読の内容です(無料なのでサクッと読んじゃってください♪)。
■詳細はこちらから↓